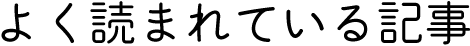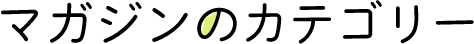SYOEIMAGAZINE

2025[Fri]
06.06
【現場日記】緑区N様邸 ①
本日は、緑区での現場の様子をご紹介させていただきます。
今回は、更地の状態から基礎工事終了まで、普段はあまりじっくり見る機会のない現場の裏側や様子をお届けいたします。
昨年、古家を解体し、秋ごろから本格的に家づくりの計画がはじまったこちらの現場。
設計士や現場監督が何度も現場に足を運び、隣家や周りの環境をチェックしていくところから始まります。

まずは擁壁が古くなっていたため、擁壁のやり替えから行います。
擁壁のやり替えが必要かどうかは、建築士が診断していきます。


着工前には、施主様と設計士、現場監督、弊社代表も参加して地鎮祭を行いました。
地鎮祭とは、土地の神様に土地の利用を許してもらうよう祝い鎮める儀式のことです。
一般的に地元の神社の神主さんに、地鎮祭の祈祷をお願いします。

地鎮祭では、下記を準備して進めていきます。
-
・祭壇
-
・しめ縄
-
・榊
-
・三方
-
・半紙
-
・お供え物(米、酒、塩、水、海の幸(尾頭付きの魚)、山の幸(野菜・果物))
-
・※初穂料(施主様が用意)
-
- ※以外は全て神社が用意(菊名神社の場合)
-

まずは基礎工事を始めるにあたり、「水盛り(みずもり)」という工程からスタートしました。
「水盛り」とは高さの基準となる水平を定めることで、レーザー計測器を使い「水糸」を張っていきます。

建物の位置、高さ、深さなどを標示する、とても大切な工程のため、何度もチェックを行います。
続いては、基礎の部分の土を掘削する「土工事(どこうじ)」。

砕石を敷き込み、ランマーと呼ばれる機械で固めていく作業を行います。
ここから、基礎と地盤の間に施す工事「地業(じぎょう)工事」を進めていきます。

給水管・給湯管・排水管を建物に取り込む位置に、部材を設置。

こちらでは、敷地の高低差をカバーするために、通常よりも深く基礎を施工する「深基礎」と呼ばれる工程をしていきます。

何カ所もチェックを重ねます。
こちらはかぶり厚さと言って、鉄筋が錆びにくいようにしっかりとクリアランスを取っています。

深基礎をつくりながら、続いて地盤からの湿気を遮断する防湿シートを敷き込み。
破れがないか、くまなく確認してまわります。
ビニールが曇っているのは、湿気が上部に上がらないよう、うまく遮断されている状態です。

コンクリートを打設後、基礎の立ち上がり部分になる「型枠」を固定。

ここで、謎のボックスが何個も登場!
少し特殊なこちらも「深基礎」。
基礎の内部の立ち上がりを極限まで省くことができるため、コストを抑えるだけではなく、
建物の力を基礎に無駄なく有効に伝えることができます。
こちらの木枠は、基礎屋さんが一個一個手作りし、作成したものです。


コンクリートが固まった後の様子が少し可愛らしいです。

玄関に続く階段の基礎を取り付け、基礎工事も終盤に入ります。


松栄では、外部による第三者の監査チェックを依頼しており、基礎工事の段階では2回、監査のタイミングがあります。
なかなかじっくりと見ることのない現場の様子。
いかがだったでしょうか?
今回は更地の状態から基礎工事までをご紹介しました。
ここからいよいよ、建物の骨組みにあたる「躯体」の工事が始まります。
現在も現場は動いていますので、安全に気を付けて進めていき、引き続き現場の様子をご紹介できればと思います。
以上、現場日記をご覧いただき、ありがとうございました!
松栄では、お客様の希望エリア・予算に基づいた「良い土地の探し方」や、
暮らしのイメージを考える中で「どのように家づくりを始めたらよいか」など、
家づくりに対する疑問に、いつでもお答えします。
いつも通り、こちら側からは一切営業はしませんので、いつでもお気軽にご来店ください!
-

年間10棟、車で30分限定の施工管理職募集!
2025.12.27 -

【大倉山】富士山が見える2階リビングの家
2024.9.13 -

東白楽 わんこそば たち花
2014.12.1 -

家事ラク×共働き×収納力の家 緑区白山の注文住宅
2026.2.5 -
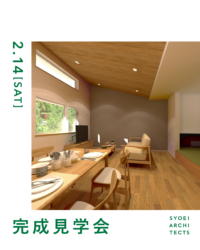
2/14(土)に妙蓮寺にて完成見学会を開催いたします! 【満...
2026.1.23